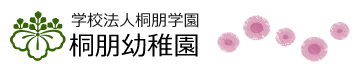5歳児 友だちが仲間になっていく
園だより |
子どもたちの園生活は、1日として同じ日はありません。特に、自然環境が私達の日常に、もたらしてくれる変化や潤いは、心揺さぶられることが多いです。
6月末の出来事です。
ゆり組テラスのコルク積み木で遊んでいた4人の男の子が大騒ぎを始めました。
Aさん 「何かいた。何かいた。トカゲみたいなのがいた!! ここに入り込んだ! この靴箱を動かしてほしいの!」
レインコート掛けやバケツを動かして、トカゲの姿を探しますが、出会えませんでした。
この時、私は、トカゲはきっと、外に逃げてしまったのだろうと思いました。しかし、Aさんはじめ、子どもたちは違いました。この下はどうか?あっちはどうか?と探し続けます。
随分長い時間、テラスで探し続けていると
「いたーーーーーーーーーーーーー!!!!」とBくんが叫びます。
「そっち、そっちに入った!!」
そして、Aくんのまなざしが一変し、自分の中にあるすべての集中力で、トカゲを捕まえました。その時のAさんのただならぬ動きを目の前に、私も全速力で虫かごを探し、Aくんとの連携プレー?!で、何とか虫かごの中に、トカゲを入れることが出来ました。
早々に諦めていた自分が恥ずかしく思えました。
「もう一度出会いたい。」「何としても、捕まえたい」という子どもたちの熱意や執念、粘りに感服しました。そして、全速力で虫かごを探し、虫かごに入れるという最後の一手に関われたことで、自分自身も“トカゲ探しボーイズ”(心の中でそっと命名)の仲間に入れてもらったような気持ちになり、思わず彼らとハイタッチをしていました。(トカゲちゃん、ごめんよ という気持ちを併せ持ちながら)

さて、この小さな小さなトカゲちゃんは、なぜこんなにも“トカゲ探しボーイズ”や大人の心を奪うのでしょう。理由は、とても小さいのに、体の色が美しく、そして俊敏に動くからでしょうか。調べてみると『ニホントカゲ』の子どもです。降園間際の出来事だったことや、子どもたちの粘りを見ていた大人としては「逃がしてあげよう」とはどうしても言えず、子どもたちと対話した結果、私が明日の朝まで様子を見ること、万が一、弱っていそうな場合は、逃がす場合もあるということを約束して、その日の保育を終えました。
重責を担ったので、虫かごに土や枯葉を入れて、何とか明日の朝まではと家に持ち帰り、生存を確かめつつ、無事に翌朝、子どもたちにその元気な美しい姿を再び見せることが出来ました。その日の朝、テラス掃除をしていた別の保育者は、トカゲちゃんとうりふたつの別の個体のトカゲちゃんに出会いました。まるで、昨日からはぐれている家族を探しに来たかのようです。朝の集まりの際に、昨日から何もエサをあげられていないが、それでも生きていることに安堵するが、今朝、このトカゲちゃんの家族が、この子を探しに来たようだったという話しをしてみました。(内心では「というわけで、逃がしてあげましょうよ」という展開を願いつつ、話をしました)ところが・・・
「それは、かわいそうだ。じゃあ、トカゲの家族を、カゴにもう一匹捕まえてあげよう!! 生きている虫を捕まえて、エサも入れてあげるぞ! エイエイオー!」
と、子どもたちは口々に決意表明し、別の方向に心を合わせて、進み始めてしまいました。私ともう一人の保育者はこの展開に顔を見合わせつつ、あと数時間だけ、子どもたちの様子を見守ることにしました。

それから1時間が経ちました。Aくんはじめ、“トカゲ探しボーイズ”が、涙ながらにゆり組にテラスに戻ってきたのです。空っぽの虫かごを手に、茫然としています。
理由を聞くと、中休みに畑に来た小学生がもっと大きなトカゲを捕まえていて、見せ合って交流していた。「それは、赤ちゃんだから、飼うのは難しい。死なせてしまうだけだから、逃がしてあげた方がいいよ」とアドバイスしてくれたとのこと。すると、別の小学生が急に、“トカゲ探しボーイズ”が手にしていた虫かごを取り、トカゲを逃がしてしまったのだそうです。恐らく正義感からと思われますが、その突然の出来事に、困惑し、悲しさと悔しさを抱えながら、虫かごを手に帰ってきたのです。なんとかわいそうな“トカゲ探しボーイズ”でしょう。無念さが伝わり、いたたまれなくなりました。そこで、
「逃がしてあげた方がいいのは分った。けれど、逃がすなら、自分たちでやりたかった。勝手に逃がされたのは、とても悲しかった」
と小学生に抗議しに行くことにしました。
「よし、じゃあ、言いに行く時に頼んでみよう。僕たちのトカゲの赤ちゃんを逃がしたんだから、その代わりに、このタマムシと、小学生の大きなトカゲを交換してほしいって言ってみる!!」
とCくんが意気込んでいます。タマムシは美しい色ですが、すでに亡くなっています。つまり、抗議の後の要望は、『息絶えている美しいタマムシと、生きていて自分たちが捕まえたのよりも大きなトカゲを交換してほしい』という規格外の交渉事です。
“トカゲ探しボーイズ”は、空っぽの虫かごを手に、隊列を組んで緊張した面持ちで、5年生に思いを伝えに行きました。市川のその時の内心は「この交渉は、叶わないでしょうね・・・。そのあと、どうしよう・・・」と考えを巡らせつつ、まずは、抗議内容について、伝えました。すると、
「わかった。ごめんね」
と言ってもらいました。子どもたちは、悲しいけれど、納得したという表情を浮かべています。さて、もう一人の虫博士の手には、トカゲがいます。トカゲの身体をなでながら、愛でています。そのお兄さんを前に、いよいよ例の交渉ごとを伝えます。すると、お兄さんはトカゲをなでながら言いました。
「うん、いいよ。それは構わないよ。ただし、条件がある。トカゲは、明日には、畑に返してあげること。出来たら、これよりも大きな飼育ケースに入れて、もぐれるように土とか入れてあげて」
と言われ、亡くなっている美しいタマムシと、トカゲとを無事に交換してもらい、足取り軽く幼稚園に戻ってきたのでした。経験豊富なお兄さんのアドバイスは子どもたちにスッと入り、翌日の降園時、約束通り、畑にトカゲを逃がしました。「バイバーイ」とたくさんの子どもたちに見送られながら。
トカゲちゃんとの出会いをきっかけに、この3日間、次々に起こる変化に心揺さぶられながら過ごしました。そのすべては子どもたちの経験となり、その経験を友達とくぐっていくことで、お互いを知り合い、仲間になっていくんだなと感じました。仲間に入れてもらいながら、私自身もそのことを実感しつつ、実に面白い世界に身を置かせてもらっているなと感謝が沸き起こります。

一番の年上のゆり組に進級して4か月。
子どもたちが共にしてきた心揺さぶられる出来事を積み重ねて、さらにお互いの声を発信しあう子ども集団に成長していることを感じます。耳を傾けて、仲間に寄り添う姿もあります。友だちが仲間になり、関係性が深まる2学期には、どんな出来事が待っているのかな、と引き続き子どもたちとの日々を楽しみたいです。