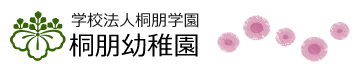4歳児 ごめんねまでの時間
園だより |
6月下旬のある日、お弁当を食べ終えて園庭にいた時のことでした。
Aくんが私の元にやってきて、「先生!Bさんが叩いた!」と穏やかでない表情でいうのです。それは困った、どうしてだろうね、話を聞きにいってみよっか。と2人でBさんのいるアスレチック付近へ向かいました。理由を聞いてみると、BさんがもっていたピーマンをAさんが取ったから嫌だった、だから叩いたということでした。
確かに数分前にどこからともなく(きっと畑から)ピーマンが1つ、子どもたちの手に渡ってきているのを私も目にしていました。ああ、あのピーマンか、と納得したところで「違う!そのピーマンは元々僕がもっていて、それを小学生にあげたんだ!だから僕のだったんだ」とAさんがいいます。
大人の私はピーマンは誰のものでもないと思うけどなー、育てたのは小学生だしなーと思いましたが、そんな事言った所で納得してくれないのは目に見えています。理由はあったとはいえ叩いてしまうのはよくなかったねという事と、経緯を要約して両者に伝え、お互いの気持ちを代弁してみましたがスッキリしないお顔です。
そしてさらにAさんは言います。「今ごめんねしてくれないと許さない」と。しかしBさんはというと、謝る気なんてさらさらない様子です。
困りました。険悪なムードです。

そんなところに訪問者が…!
ミミズです。Bくんの足元にミミズがいたのです。しかも2匹。それをみて2人は怒っていたのもすっかり忘れ、お互い笑い合いながらミミズを捕まえ始めました。なんだかすっかり楽しく遊び始めた事だし、“次は叩かないでお口で伝えようね”と話して終えようかと思った矢先、「今ごめんねしないと許さないからね」とAさんは喧嘩していた事を思い出しました。するとそれを聞いたBさんは言いました。「僕はCさんとDさんのパワーがないとごめんねできないんだ」と。
CさんとDさんはその場にはおらずこの一件とは全く関係ありませんでしたが、普段からBさんととても仲良くしている仲間です。私はCさんとDさんのパワーをどのように貰うのか興味が湧いたのもあって、その2人を呼びにいこうかと移動しました。その間Aくんは口をとんがらせていましたが、一緒についてきてくれました。
さて、みんな集まってくれたところでBさんはどうするのかな、と様子をみていました。
そもそも絶対に謝らせないととは思っておらず、表情などをみながら「ちょっと今すぐには言えないみたい」「悪かったなって思ってると思う」とこちらが代弁したり、手をとって叩いた箇所を一緒に撫でてみたり、一度その場を切り上げ時間をあけて気持ちが落ち着いたところで再度促してみたりすることもあるのですが、今回はここでもまたさらにAさんが「今言わないと許さない」と気持ちを伝えてくれていて「パワーがあればできる」というBさんがいたので、橋渡ししている所であります。

するとBさんは言います。
「言えないー」と。
役者は揃ってはくれましたが、それでもやっぱり言うのは難しいみたいです。それくらい口に出すのは勇気のいることなんですね。大人でもそんな時があるのでわかる気がします。
それをみたCさんがBさんの手をそっととり、「僕が代わりにごめんねしてあげよっか?ごめんね」と、まさしくパワーを貸してくれたのです。Bくんもきっと心強く思ったことでしょう。私は「Cさん、ありがとう。Bさんすっごく嬉しいと思う」とお礼を伝えました。
それでもBさんは「言えない~」「むり~」と話しています。
ここまでで時間もだいぶ経っているので、しびれを切らし始めた私が口を出しそうになったその時、Fさんが「待っててあげるよ」と一言。さらにCさんが「がんばれー」と。ハッとさせられた言葉でした。すぐ結果を欲してしまう大人側のよくない所がでてしまったと思いました。Fさんは普段は自分のペースを大切にしている所もある子だったので、「待ってるよ」と言ってもらえる喜びを知っていたのかもしれません。

今回の事例で様々なことを考えました。
1つはトラブルの際に自分の力だけで解決することも大切ですが、幼児期においては「困ったときに助けを求めることができる」事の方がもっと大切な力なのではないかということです。「助けて」といえることは、自分の気持ちを大事にできている証拠であり、そして信頼できる人に助けを求める経験は子どもに安心感や自己肯定感を育みます。そうした積み重ねが、やがて自分で考え、行動できる”本当の自立”へと繋がっていくのだと思います。「困ったらひとりで頑張らなくていいんだよ」という声かけで、安心してヘルプを出せる土壌を一緒に育んでいきたいものです。
そしてもう1つは、「ごめんね」と代わりに伝えてくれたCさん、「待ってるよ」と伝えてくれたFさん、そして困っている仲間に頭を寄せ合ってくれていたCさん、Dさん、Fさんたちの行動はどこからくるのだろうかと考えた時に、きっとこれまでに自分自身が大人や仲間に優しくされたり気持ちに寄り添ってもらった経験が心に残り、それが自然と他者に向けられたのではないかと思いました。そういう経験を繰り返していく中で子どもが自分の中に徐々に取り入れ、自分自身の力にしていくのではないでしょうか。と思うとやはりまずは大人自身がやさしさを体現するモデルになっていきたいとも感じました。
今回は、ごめんねの言葉をきいたAさんがすぐに「いいよ」としてくれたので和解に至りました。Aさんもここまで時間をかけて言葉を紬出したBさんの姿をみていたからこそ、すぐに受け入れてくれたのだと思います。
お騒がせなピーマンもいつの間にか見当たらなくなり、後を引きずることもなかったのでほっと一安心したのでした。